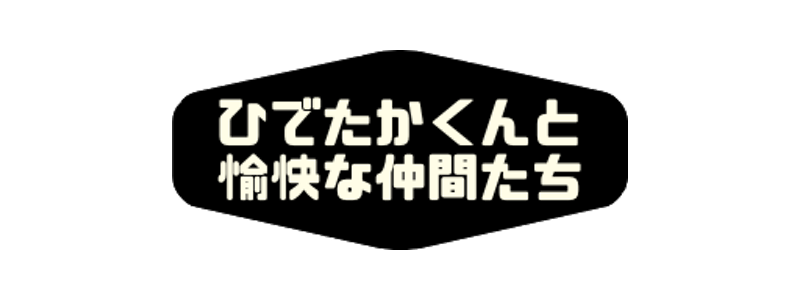アニメ・ゲーム関連のラジオ、通称”アニラジ”は、1990年代の多くのアニメファンにとって青春の象徴であり、特別な文化を築いてきました。2025年のゴールデンウイークにそんなアニラジ、特に『文化放送A&Gゾーン』の黎明期から関わってきた伝説的なパーソナリティ、作家、プロデューサーたちが集結する貴重なイベントが『エモエモ90’s』の主催で開催されました。懐かしい思い出話から業界の裏側まで、「イベント外での口外は禁止」と銘打たれた熱気に満ちたトークが繰り広げられました。
※本記事は演者様方の許可を受けた上で制作されています
イベントは昼と夜の2ステージ。参加者の皆さんは特別なオリジナルメニューのドリンクやフードを楽しむ和やかな雰囲気でイベントは始まりました。参加者の中には「遠方から駆けつけた!」「暗い青春を思い出すために来ました」 と語る方も。「90年代のアニラジを聞いたことがない」という方も。そんな参加者のアニラジへの想いもイベント中に沢山、寄せられました。
エモエモ90’sとは?

『エモエモ90’s』は、声優・ナレーターの榎本温子さんと、声優・歌手・作詞・作曲家の桃井はるこさんが運営しているYouTube番組です。番組のコンセプトはアニラジテイストで、1990年代の声優文化、音楽、アニメカルチャーなどをテーマに、二人が自由に語り合うスタイルです。
・榎本温子(写真:左)
声優、ナレーター。アニメ『彼氏彼女の事情』の主役・宮沢雪野役で声優デビュー。『ふたりはプリキュア Splash☆Star』『キボウノチカラ~オトナプリキュア‘23~ 』(美翔舞役 )、『カードファイト!! ヴァンガード』(先導エミ役)ほか多数に出演。Abema Primeのメインナレーターも務める。90年代はアニラジの公開収録に積極的に参加していた。
X
YouTube
〜榎本温子インタビュー記事〜
榎本温子 インタビュー前編|声優業界での挑戦と成長
榎本温子 インタビュー後編|声優・ナレーターとして活動を続けるための哲学
・桃井はるこ(写真:右)
声優、歌手、作詞、作曲家。「元祖アキバ系女王」の異名を持つ。高校在学中にインターネットに掲載していた日記が雑誌編集長の目に留まり雑誌に連載開始。2000年には『Mail Me』でシンガーソングライターデビュー。アイドルやアーティストへ楽曲提供も。声優としての出演作は『STEINS;GATE』(フェイリス・ニャンニャン役)、『テイルズ・オブ・ジ・アビス』(アニス・タトリン役)、『ポケットモンスター ピカピカ星空キャンプ』(ソーナノ役)ほか多数。
実は、小学生の頃からラジオ番組全般(『伊集院光のOh!デカナイト』など)をよく聴いており、投稿して採用された成功体験によってラジオ好きになる。
X
YouTube
〜桃井はるこインタビュー記事〜
桃井はるこ インタビュー前編|音楽との出会いとヤマギワソフトの思い出
桃井はるこ インタビュー後編|音楽とオタク文化を語る
アニラジと同じ作り方で進行された!豪華な飛び入りゲストも!
イベントはアニラジと同様に構成作家ををいれて構成・台本を組んだ上で挑む気合の入りっぷり。構成作家として土井武志さんが参加しました。土井さん自身も様々なアニラジを手かげてきました。
イベントの最中にはなんと飛び入りゲストも!自身も文化放送でアニラジ『同級生 恋愛専科』を担当していたショッカーO野さん、そしてBS-i(現BS-TBS)で2003年7月から2005年3月までアニメ、ゲームグッズの通販番組『激☆店』で店長役を努めた小林治さんもフラっとマイクを軽く握りました。
アニラジ黎明期を語ったキーパーソンたち
当時のアニラジシーンを牽引した複数のキーパーソンがゲストとして登壇しましたが、それぞれ紹介していきます。(以下、敬称省略)
・おたっきぃ佐々木
ラジオディレクター、ラジオパーソナリティ、おたく。業界でのキャリアは20年以上。自身も最初は『アニメトピア』『ペアペアアニメージュ』『アニメシティー』などの80年代のアニメ雑誌がスポンサーの声優ラジオ番組のリスナーだった。大学在学中にサークルの先輩の伝手で文化放送のバイトに潜り込んだことでラジオとの関わりがスタート。1993年春より『MADARA転生編』のADを担当。同年10月、『ツインビーPARADISE』でディレクターデビューを果たす。その後はディレクターとして『緒方恵美の銀河にほえろ』『もっと!ときめきメモリアル』などを、『超機動放送アニゲマスター』などではパーソナリティーとして、多数のアニラジ番組の製作に関わりました。
・やまけん
ラジオディレクター、ラジオパーソナリティ、実業家。90年代、スパイダーアンテナを購入して地方局のラジオを聞いていた筋金入り。株式会社TRYALL、五十鈴工業株式会社代表取締役。現在は釣り関連の仕事にも携わっているとのこと。声優のレッスンも受けたことがあったがその後、MCの仕事が増えていき、ラジオにも進出。文化放送での初のレギュラー番組は『ゆうこりん』こと小倉優子さんの『小倉優子のウキウキりんこだプー!うるとらだっしゅ』で相手MC。インターネットラジオの世界にも精通。インターネットラジオサイト<音泉>の企画立案・創業者。
・山本麻里安
声優、歌手、脚本家。現役高校生であった1998年に、『彼氏彼女の事情』の宮沢花野役でデビュー。実は『「井上喜久子、17才です」→「おいおい」』のネタの起源の1人。自身が17歳の頃に井上喜久子さんとラジオ番組『かきくけ喜久子のさしすせSonata』を共にしていた際の番組内の掛け合いが起源。90年代の週末の夜はずっとアニラジを聞いていたとのこと。自宅の中で電波の良い場所を探していた想い出も。
•ドン・マッコウ(溝口功)
音響制作・イベント企画・ラジオ制作会社『ツーファイブ』の元代表取締役。自身は文化放送でレギュラー番組を持っていませんでしたが、プロデューサーとして数々の文化放送のアニラジのコンテンツに関わってきました。アニラジをプロデュースする過程ではレコード会社と放送局の間に挟まれて様々な苦労も…!
・片寄好之
文化放送でアニラジの全てを取り仕切ってきた偉い人。90年代は様々なアニラジを効率的に配置しながら企画を立ち上げました。オタッキー佐々木さんを『アニゲマスター』のパーソナリティーに任命したことにも一枚噛む。『文化放送A&Gゾーン』の名付け親 。現在は声優アワードの統括プロデューサー。
•土井武志
放送作家、構成作家。イベント制作やラジオ制作に深く関わった土井さん。元々は大阪で芸人さんのラジオを手掛けていましたが、東京に出てアイドル番組を制作。文化放送から「声優をアイドルにしたい」 と相談を受けたことが、アニラジの制作に関わるきっかけに。
文化放送以外でも様々な局でアニラジを担当。実は『「井上喜久子、17才です」→「おいおい」』のフレーズを考えた人
予算の手軽さがアニラジの誕生のきっかけか
本イベントではアニラジが発展していく歴史について当時の実体験を交えながら語られました。アニラジが発足した当時、作品をアニメ化する前段階でラジオが活用されていたようです。ラジオで受けが良かったら正式にアニメ制作に移りました。
ドン・マッコウ「当時はラジオの方がテレビより予算面で高額でなかったことも大きかったんだよ」
やまけん「アニメ本編の1期と2期の間や、OVAまでの間をつなぐような使われて方もされていたよね」
80年代のバブルが弾けた後だから各会社もそんなに予算がなかったこともアニラジの発展に影響を及ぼしたとのことです。
瞬く間に人気が広がっていたアニラジですが、最初から局内で評価を得られたわけではありませんでした。
おたっきぃ佐々木「(担当していた番組が)レーティング(聴取率)かなり良かったんだけど中々、局内で認めてもらえなくて。悔しくて空いていたスタジオでNIRVANAを爆音で流しながら酒を流し込んだこともあった。その時に機材を壊してしまっていたらしくて怒られました(笑)」
しかし、着実にアニラジ人気は拡大していき文化放送ではアニラジの数が増えていき、『文化放送A&Gゾーン』が形成されていきました。
ゲーム業界の好景気がアニラジの追い風に
90年代中頃からのエヴァンゲリオンやギャルゲーなどのブームによりゲーム業界が好景気に入ったことも『文化放送A&Gゾーン』の拡大に拍車をかけました。様々なゲーム会社がアニラジの有力なスポンサーとして多数参入したことで、潤沢な予算が投入されていきました。
当時、『文化放送A&Gゾーン』を取り仕切っていた片寄好之さんはアニラジの需要の高まりを汲み取りながら様々な声優を起用した企画書を次々とスポンサーに提出。アニラジの番組本数を急増させていきました。
片寄好之「番組編成に移った時に「私、アニメ好きじゃん!」って気づいたんですよね(笑)。そこで1995年4月から放送開始された『SOMETHING DREAMS マルチメディアカウントダウン』の見学に行ったり、番組ディレクターに色々と声優について教えてもらいながら勉強しました。アニメ作品も沢山、見ましたね。こうやって作った企画書をスポンサーに提出しました。そして『文化放送A&Gゾーン』を形成しました」
桃井はるこ「昔の秋葉原って電気店が集まってたことで賑わったじゃないですか。アニラジもゾーンってなって沢山集まると一個の番組だけよりも賑わっていきますよね」
その結果、一時期の文化放送では週末だけでなく、平日でも毎日のように長時間、アニラジが放送されました。文化放送内でアニラジはスポーツや、報道と同レベルのものにまで育て上げました。
桃井はるこ「『文化放送A&Gゾーン』ってものすごく長時間だったからカセットテープじゃなくてVHSのビデオデッキを使って、音声だけを録音してました。ステレオのビデオデッキだったので音声出力の片方は文化放送、もう片方はニッポン放送みたいなことをしてアニラジを録音して聴いてましたよ。それくらいしないと寝落ちできないくらい沢山のアニラジがあったし(笑)」
当時のアニラジリスナーは録音した番組のカセットテープをファン同士で交換していた模様です。コミュニティーを形成することで確実にアニラジという新しいジャンルが形成されていきました。
土井武志「新しいジャンルを作ろうという文化放送の流れが面白かった。当初は冷ややかな目で見られていたアニラジも、レーティングが取れるようになると社内の態度が変わった」
アニラジは時代の波に乗っていきました。
山本麻里安「公開収録を毎週末、誰かがどこかで開催してる状況だったよね」
榎本温子「往復ハガキを送り当選すれば無料で参加することができたからたくさん、応募した(笑)」
ゲーム会社が協賛金を積極的にだしてくれたことでありとあらゆる公会堂、公民館で公開収録を行うことが可能になりました。ゲーム会社としても公開収録は自社の製品のPRの場として機能しました。
やまけん「ゲームが発表されるまでの間にファンを繋ぎ止めるためのコンテンツとしても有効だった」
時にはアニラジで新作ゲームの発売延期の謝罪コーナーにプロデューサーが登場したこともあった模様です(笑)。
勢いに乗ったアニラジは大胆な企画が行われたことも!おたっきぃ佐々木さんが『超機動放送アニゲマスター』のMCを努めていた際に、土井さんの繋がりでニッポン放送のアニラジ『岩男潤子と荘口彰久のスーパーアニメガヒットTOP10』でMCを担当されていた荘口彰久さんをゲストに招かれたことも!令和の時代ではコラボは積極的に行われていますが、他局のライバル番組のMCをゲストに招くのは当時は非常に斬新な試みでした。
90年代の四谷で様々な「新境地」が誕生した

どんなに潤沢な資金があったところで、放送が面白くなければアニラジ人気は拡大しなかったでしょう。
本イベントでメインに取り上げられてる文化放送は四谷にあり、当時のアニラジの収録は毎週行われていたとのことです。収録後はスタッフとパーソナリティを務めた声優が四谷付近の飲食店での打ち上げで放送のネタを暖めていったとのことです。
片寄好之「こういう打ち上げでの交流がきっかけで緒方(恵美)が爆発して『銀河に吠えろ』のような、新境地を作っていったんだろうね」
おたっきぃ佐々木「当時、緒方さんのファンクラブの会員は女性が多かったらしいけど『銀河に吠えろ』のせいで男性が増えたらしいよ(笑)」
ドン・マッコウ「池澤春菜もお嬢様なんだけど、内に秘める凄いものがあったんだろうね(笑)。凄い爆発だった」
アニラジを通じた制作活動でパーソナリティー自身の成長も起きたエピソードが語られました。
ただ、時にはパーソナリティが放送中に過激な発言をしてしまうなどやり過ぎてしまうこともあったようで、その際に叱られるのはパーソナリティ本人ではなく、ディレクターやプロデューサーといったスタッフでした。
片寄好之「何枚、始末書書いたんだろうね(笑)」
他にも夜に放送されるものを昼に納品するようなタイトなスケジュールで放送が納品されていた、当時ならではのエピソードも披露されました。
他にも文化放送自体のユニークなエピソードも語られました。文化放送は元々キリスト教の財団法人として始まり、旧局舎では礼拝堂として作られた場所がスタジオとして使われていたことも。旧局舎が増築につぐ増築が重ねられていた結果、ミステリーハウスのような構造になっていて、中には深夜にスタジオで作業していた時に「声が聞こえた…」などの奇妙な体験をしたといった怪談めいたエピソードも披露されました。
BSデジタルラジオは採算が取れていたが…
90年代から00年代に変わる境目には、放送衛星を使用したBSデジタルラジオが登場しました。音声だけでなく数十秒サイクルで切り替わる静止画を映す機能もあったため、番組によっては様々な映像を同時に配信することもできました。
文化放送でもフジテレビの帯域を借りる形で『BSQR489』を展開して、こちらでも様々なアニラジを放送しました。本イベントのゲストの山本麻里安さんも『山本麻里安のはにわマイハウス』でパーソナリティーを努めていました。
片寄好之「BSデジタルラジオは文化放送は収益を成立させることができた。本当は文化放送は止める必要はなかったけど他が全部終わっちゃったからね…」
やまけん「帯域もフジに返さなきゃいけなくなって物理的に消滅しちゃった」
『BSQR489』が採算が取れていたことからアニラジが持つ潜在能力の高さをうかがい知ることができます。
アニラジがインターネットの世界へ
00年代に入っていく過程でテレホーダイ、ADSLとインターネットの回線が発達していきます。ドン・マッコウさんも00年代に入っていくにあたって、先鋭的な取り組みを行っていてインターネット放送で収録したものをラジオ関西に納品もされていた模様です。
やまけん「インターネット放送という概念が広がり出したよね。BSQRもだけど当時はカクカクの紙芝居だったけど。世界初のインターネット放送局を謳った『ステーションガイア』でのパーソナリティーをきっかけに仕事の幅を広げていったなぁ。アニメ・ゲームファンが楽しめるコンテンツって年々、増加の一途だったから。「ながら」で聴けるラジオ形式の方がネットで受け入れやすいのではと、ラジオ配信に力を入れて、各社さんのラジオに出演したり作ったりと関わったりしていった」
令和の今ではインターネット放送は日常的に広がり、『Radiko』を使ってインターネット経由でアニラジを楽しまれている方もいらっしゃるでしょう。しかしながら…インターネット放送は順風満帆だったわけではありません。
ドン・マッコウさんは自ら企画書を書いてインターネット放送を立ち上げましたが、番組を開始すると同時に予想を超えるアクセスが集中していしまってサーバーがダウンしてしまって番組進行に大きな支障がでてしまったことも…!
ドン・マッコウ「もう大変でさぁ…「お前ら1回落ちろ」「リロードすんな」ってせっかく集まってくれたみんなに言うことになっちゃったんだよ」
やまけん「『ステーションガイア』でも、その当時に最も強固だったサーバーを導入してみたけどアクセスを支えきれなかったからね」
現代のYouTubeのような強固なサーバーでしたら世界中の人々がネット配信をしても受け止めきれますが、00年代初頭辺りではそうはいかなかったのです。
収益体制の構築も一筋縄でいかなかった模様です。
やまけん「今って「サブスク」の概念があるじゃん。でも当時は「有料コンテンツ」という感じで月額制だったりという販売方法が中心だった。ネット=無料といった空気感も相まってどこも厳しいという感じだった」
ドン・マッコウ「うちは(制作費回収のために)コミケでカセットテープ販売しがちだったな。儲からなかったけど(笑)」
やまけん「経営センスがメチャクチャでしょ(笑)」
インターネットの世界でも収益モデルを確立していくアニラジ
やまけんさんはインターネットラジオステーション<音泉>の立ち上げに着手していきました。
やまけん「その後、「無料で(インターネット放送を)ちゃんとやったらいいんじゃないか」という発想から、インターネットラジオステーション<音泉>の仕組みを考えた。ユーザーからの直接課金は将来的に定着してからで、スポンサーになってもらうコンテンツメーカー側のお財布からの出費で番組が制作出来る方法を考えた。
地上波の番組ってスポンサーがお金を出していても番組自体は放送局の著作物になるから自由に使えないんだよ。そこで収録した番組をスポンサーに渡すことにした。収録した番組の著作権まわりと声優さんの2次使用料などもクリアした上でね」
スポンサーへの様々な提案をすることで制作費を集めていきました。
やまけん「スポンサーに渡したものはDVDとかのいわゆる「円盤」の特典に使ってもらったり、なんなら音声を売ったり。こうすることで通常もらう宣伝費以外からも制作費をもらえるモデルを作った」
インターネットラジオステーション<音泉>は制作面での利点もありました。
やまけん「地上波と違うから時間設定も「きっちり」じゃなくて「だいたい」でOK。環境が緩いし、電波法や自主規制もないから音声の整えも少し緩くて大丈夫だった。マシン上でライトに制作して、業務用機器を通さなくて良いから地上波よりは安く作れたんだよね」
やまけんさんはインターネットラジオステーション<音泉>プロデューサー、構成作家、ディレクターを兼任し、一時期は15番組以上を一人で担当していました。多忙を極め、スタジオの空き時間に段ボールを敷いて仮眠を取ることもあったと語っています
やまけん「とも蔵(川上とも子さん)の番組だったな。オレは疲れて仮眠取ってるのに誰かがメッチャ喋っていて「うるせぇなぁ…!」と思って目を開けたら番組の収録してんだよ。しょうがないから寝起きで番組に参加した」
インターネットラジオステーション<音泉>も順風満帆なスタートだったわけではありません。
やまけん「スポンサー集めるために企画書を作って知っている数社に持ち込んだけど、当初は「ネットでしょ?そんなの廃れるよ」なんて頓珍漢なことを言う経営者も多かった。そんな中、コスパグループから声がかかり、創立と同時にグループ会社の最高執行役員扱いで入社という流れでだった」
榎本温子「今じゃ大インターネット時代なのにね」
やまけん「インターネットがまだ「アングラ」と思われていたからね。声優さんにオファーしても、所属している事務所によっては「弊社のタレントはネットに声を一切載せません」って言われたり雑に扱われて辛かったよ。新ビジネスモデルの理解もなかなか進まず苦労したけど、とにかく「聴取数」という圧倒的な武器があったので、徐々に「ネットラジオありだよね!」という空気になっていったのは嬉しかった」
編集後記
いかがでしたでしょうか?筆者はアニラジで作られた文化は、現在のYouTuberをはじめとした様々な配信サイトにも根付いているように感じます。例えば
『「井上喜久子、17才です」→「おいおい」』
このネタを配信中に言われるVTuberを見かけることが多くないですか?アニラジで誕生した様々なミームは現在、インターネットのあらゆるところに広がって行きました。
いつかエモエモ90’sのイベントで「アニラジと、00年代以降の配信文化」をテーマに語ってほしいと思いました。
他にもアニラジの誕生の背景として「TVより予算が安かった」という点があったことが印象的でした。
その後のアニラジが流行っていく過程は、MLBのオークランド・アスレチックスが過小評価されて選手を見出すことでコストを抑えて成果を出していったマネーボールみたいに感じました。アニラジのビジネスモデルを学ぶことからヒントも多いだろうと思いました。